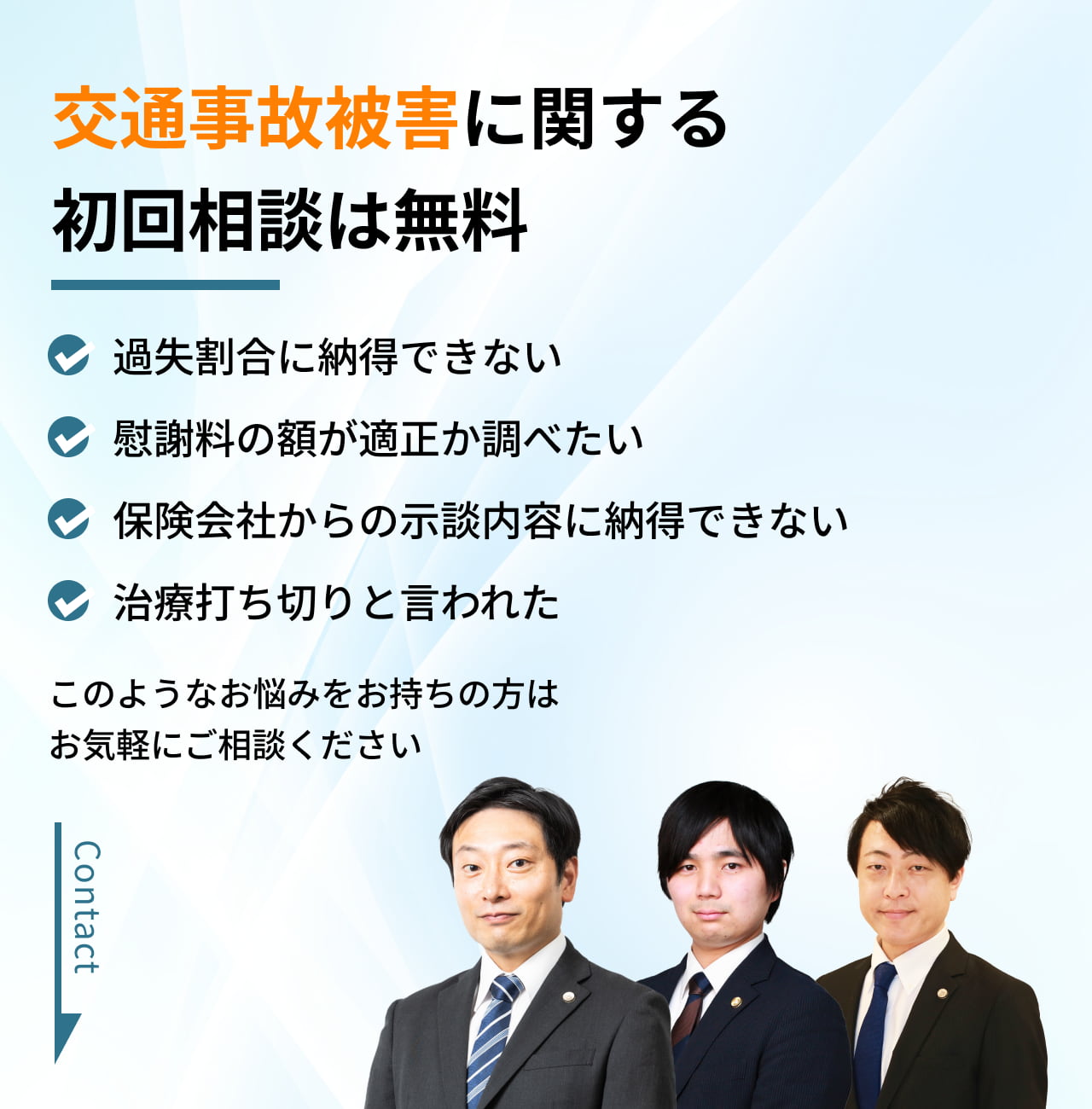目次
交通事故後の死亡診断書の死因の記載について ~死亡事故の証拠保全~

交通事故は突然起こるものであるところ、大切な方がお亡くなりになった場合、葬儀関係や行政関係、銀行関係を含む相続関係など、やらなければならないことがたくさんあります。
悲しみに暮れる間もないほどで、心身ともに疲れ切ってしまう方が多いです。
ただ、このときに証拠保全の関係で注意していただきたい事項がいくつかありますので、その点についてご説明させていただきます。
死亡診断書の死因欄の記載について
まずもっとも注意しなければならないのが、病院に書いてもらう死亡診断書の死因欄の記載についてです。
一つには「死亡の原因」という項目があり、その中には、直接死因が何か、直接死因の原因が何か、直接死因の原因の原因が何か・・・といったように病因を連続的に各項目と、直接には死因に関係しないがこれらの傷病経過に影響を及ぼした傷病名を書く項目とがあります。
この項目欄には、最終的には外傷(=交通事故)に起因する傷病名につながっていなければなりません。
もう一つには、「死因の種類」という項目があり、病死及び自然死、交通事故、転倒転落、溺水、煙・火災及び火焔による傷害、窒息、中毒、その他不慮の外因死、自殺、他殺、その他不詳の外因死、不詳の死といった分類分けがなされております。
こちらも当然ながら、「交通事故」という分類に印がなされていなければなりません。
この2つの注意点のいずれかがクリアしていない場合には、その後の示談交渉や裁判で交通事故と死亡との間に因果関係が無いものと争われ、交通事故後に生じた結果と認められた損害額との間に大きなかい離が生まれてしまう可能性があります。
交通事故に遭ってからお亡くなりになるまでの期間が短ければこのような問題が生じることは無いことが多いですが、交通事故に遭ってからお亡くなりになるまでの期間が開いている場合には注意しなければなりません。
死亡診断書の死因欄に、交通事故と記載がない場合
では、もし外傷に起因する傷病名が記載されていなかったり、死因の種類について「交通事故」と明示されていない場合には、どうすればよいでしょうか。
一つには病理解剖をするという選択があります。
病理解剖とは、病気で亡くなった方を対象に、臨床診断が妥当か否か、直接死因やその原因の判断が妥当か否かといった点を目的にして、系統的な解剖を行うことです。
交通事故後にお亡くなりになったけれども「死因の種類」について「交通事故」と明示されていない場合、「病死及び自然死」と明示されていることが最も多いです。
病理解剖は体内に侵襲するものでありますが、解剖によって体内を直接見ることができますので、本当に病死なのか、本当に病死だとして病死の一因に交通外傷は見られないか、というものを直接確認することができます。
もっとも、亡くなった方の体に傷をつけたくないという方もいらっしゃいます。
そのような方にはせめて「Ai(=オートプシー・イメージング)」をしていただくように勧めます。
Ai(オートプシー・イメージング)死因を調べる画像診断
Aiとは死亡時画像診断といって、CTやMRIなどによって撮影された死後の画像により、亡くなった方の体にどのような病変(特に外傷性の変化)を生じているのかを診断することによって、死亡時の病態を把握したり、死因の究明に役立てる検査方法です。
病理解剖の結果とAiの結果が整合しないことも多々あるようですが、証拠保全のためにも、因果関係が争われる可能性があるのであれば、せめてAi、画像診断だけは受けていただきたいと思います。
2024年9月からは、Aiの適切な運用と活用を推進することを目的として、Aiの撮影を実施している施設を「Ai撮影参加施設」、さらに適切な運用および管理体制にある施設を「Ai認定施設」として認定する制度が開始されました。
Ai認定施設の一覧については、以下のオートプシーイメージング学会のURLより確認が可能です。
Ai認定施設の一覧はこちらまとめ
交通事故後に亡くなった場合、死亡診断書の死因欄の記載は非常に重要です。「死亡の原因」や「死因の種類」に交通事故に起因する内容が明確に記載されていないと、後の示談交渉や裁判で交通事故との因果関係が否定され、不利益を受ける可能性があります。
もし適切な記載がされていない場合には、病理解剖やAi(オートプシー・イメージング)を活用し、死因の解明と証拠保全に努めることが大切です。特にAiは、遺族の心理的負担を軽減しつつも、外傷性の証拠を確保できる有効な方法です。
大切な方を失った悲しみの中での対応は大変ですが、必要な証拠を保全することで、適正な賠償と法的解決への一歩を踏み出すことができます。
お困りの際は、弁護士法人グレイスへお気軽に相談ください。