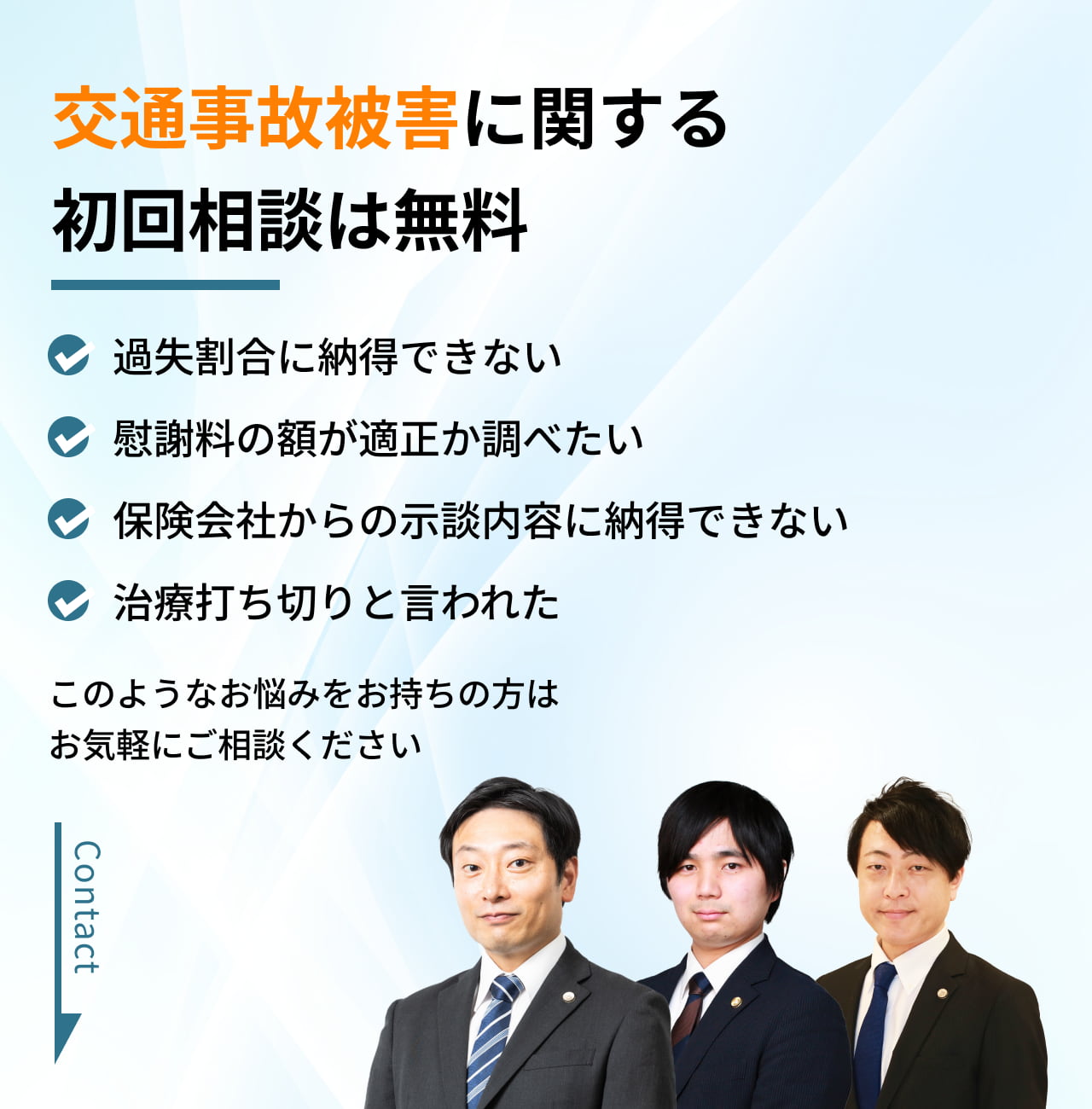目次
過失割合とは?
交通事故は、いつ、誰にでも起こりうるものです。万が一、不幸にも事故に遭われた場合に、多くの方が直面するのが「過失割合」の問題でしょう。過失割合は、事故後の損害賠償額に直接的に影響するため、その決まり方や、提示された割合に納得できない場合の対処法を正しく理解しておくことは非常に重要です。
特に、交通事故における過失割合は損害賠償請求という民事上の話ですから、いわゆる違反点数や反則金の有無などの行政処分や刑事罰とは無関係に決まりますから、注意が必要です。ゴネ得を狙う相手方に負けることなく、過失割合の基準や計算方法を知っておくことで、自衛を図りましょう。
この記事では、弁護士の視点から、過失割合の基本的な考え方から、具体的なケース、そして万が一の際に適切な対応を取るための方法まで、詳しく解説していきます。
過失割合の決まり方
過失割合とは、交通事故の当事者それぞれが、事故発生に対してどの程度の責任(不注意・過失)があったかを、数字で示した割合のことです。
例えば、「相手:80、自分:20」という過失割合であれば、相手に8割、あなた自身に2割の過失があったと判断されることになります。この割合に基づいて、最終的に支払われる損害賠償額を何割負担するかが決定されます。
過失割合についてはこれまでの裁判例が集積しており、別冊判例タイムズ38号という冊子に一定の判断基準がまとめられています。裁判官も弁護士も、この判断基準に則って過失割合に関する検討をするのです。ちなみに、過失割合は、自己車両・相手車両の種類と事故状況から大まかに決定され、事故時に特別の不注意・過失があるかどうかで微調整をするという方法で決まります。
過失割合が決まるタイミング
過失割合は、交通事故が発生したのち、事故状況が明らかになった段階で、相手方の保険会社が提示してくることがほとんどです。但し、これに応じる義務はありませんので、相手方が提示する過失割合とあなた自身が考える過失割合に差がある場合には、交渉を続けることとなります。
いずれにしても、示談終了時までに過失割合を決める必要があります。
物損事故であれば比較的早期に提示されることもありますが、人身事故の場合は、治療や後遺障害認定がある程度進み、損害額が確定に近づいてから提示されることもあります。
パターン別の過失割合
ここでは、パターン別に、簡単に過失割合を解説します。
自動車同士またはバイク同士の事故
自動車同士またはバイク同士の事故であれば、対等な運転者間の事故になりますから、事故の態様や事故状況によって過失割合が決まります。代表的な事故の過失割合は、以下のとおりです。
追突事故
基本的に追突された側:0、追突した側:100となることが多いです。追突された側に正当な理由のない急停止などの過失があった場合には、過失割合が変わります。
信号機のある交差点での事故
青信号進行車と赤信号進行車の衝突:信号無視をした側が100%の過失となるのが原則です。
青信号直進車と右折車の衝突:青信号で直進していた車:20、右折車:80が基本となることが多いです。直進車優先の原則が適用されます。
信号機のない交差点での事故
広路と狭路の交差点:広路車:30、狭路車:70など、道幅の広い方が優先される結果、道幅の狭い車の方が過失が大きくなります。
一時停止規制のある交差点:一時停止規制のある車:80、一時停止規制のない車:20といった形で、一時停止規制のある車が、より大きな過失を負うことになります。
自動車とバイクの事故
基本的な考え方は自動車同士の事故と同様ですが、バイクは自動車に比べて身体が保護されていない分、より大きな損害を受けやすいという特性があります。そのため、生じた損害を当事者が公平に分担するという損害賠償の基本理念から、バイク側の過失が自動車より低く修正されることとなります。
このため、上記自動車同士・バイク同士の交通事故の事故と比べて、5~10%ほどバイク側の過失が軽く修正されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
バイクと車の事故の過失割合を状況・ケース別に解説自動車と歩行者の事故
自動車と歩行者の事故では、道路交通法上優先されており、かつ、事故時の損害が大きくなりがちな歩行者(「交通弱者」と呼ばれることもあります。)の過失が小さくなります。代表的な事故の過失割合は以下のとおりとなります。
横断歩道上での事故
歩行者:0、自動車:100となるのが原則です。自動車運転者に横断歩道近くに歩行者がいる場合の徐行義務及び横断歩道横断者がいる場合の停止義務がありますとおり、横断歩道上の歩行者への注意義務が重く課せられている結果といえます。
信号無視の歩行者
歩行者が赤信号を無視して横断した場合でも、歩行者:70、自動車:30が基本となり、自動車側に全く過失がないとは扱われないので注意が必要です。もちろん、道路状況などによって過失割合は変動します。
道路上への飛び出し・横断
基本的には、歩行者:20~30、自動車:70~80となります。歩行者にも横断歩道がない道路を横断した帰責性があるため、過失割合は歩行者側も生じることとなります。
過失相殺について
過失相殺とは、交通事故の損害賠償額を算定する際に、被害者側にも過失があった場合に、その過失割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。
例えば、総損害額が100万円で、被害者の過失割合が20%と判断された場合、被害者が受け取れる賠償額は80万円(100万円×(1-0.2))となります。過失相殺は、公平な損害の分担を目的とした民法の規定に基づくものです。
過失割合に納得できない場合
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、いくつかの対応策があります。
相手方の保険会社に異議を申し立てる
まずは、相手方の保険会社に対して、なぜその過失割合に納得できないのか、具体的な理由(ご自身の主張を裏付ける証拠など)を添えて異議を申し立てましょう。事故状況を詳細に説明し、修正要素がある場合はそれを明確に主張することが重要です。
弁護士であれば、相手方保険会社に対して意見書を送付することもあります。特にドライブレコーダーがあれば客観的な事故態様・事故状況が明らかになりますから、有益な証拠となります。
保険会社同士で再協議してもらう
次に、ご自身が任意保険に加入している場合には、ご自身の保険会社に連絡して相手方の保険会社と再協議してもらうよう依頼することができます。保険会社は交通事故のプロですので、専門的な知見から交渉を進めてくれることが期待できます。
但し、再協議の内容や交渉の中身が見えないことはデメリットとなります。相手方との交渉内容を理解しながら進めたい場合には、後述するとおり、弁護士にご相談・ご依頼される方がよいでしょう。
弁護士に相談・交渉を依頼する
上記の方法でも解決しない場合や、ご自身での交渉に不安がある場合・交渉内容をきちんと理解したい場合には、弁護士への相談・交渉の依頼を強くお勧めします。弁護士は、以下のような点で大きな力を発揮します。
客観的な視点での過失割合の検討
弁護士は、事故状況や証拠に基づいて、法的に妥当な過失割合を客観的に判断した上で、あなたに助言することができます。
専門的な知識に基づく交渉
保険会社は、自社に有利な形で交渉を進めようとすることがあります。弁護士は、交通事故に関する豊富な知識と経験に基づき、適切な根拠を提示して保険会社と対等に交渉を進めます。
証拠収集のサポート
事故状況を裏付けるドライブレコーダーの映像、目撃者の証言、警察の調書などの証拠収集をサポートします。特に当事務所では、事故現場に赴いて証拠収集するという点を重視しています。現場百遍、まさにそこに証拠があるのです。
訴訟による解決
交渉が決裂した場合でも、訴訟を提起して裁判所で過失割合の判断を求めることができます。
物損と傷害の過失割合
当事務所では、物損において過失割合で合意し、すでに示談しているとうケースであっても、傷害の交渉の際には、一から過失割合を検討し、適正な過失割合で示談できるように交渉を進めていきます。そのためには、事故現場に行ったり、場合によっては警察の実況見分に立ち会うことも厭いません。
実際に、物損において2対8、1対9で示談していた案件が、当事務所が関わることにより、傷害の示談の際には過失割合が1対9、0対10になったというケースも多数あります。
わずか10%の差ですが、傷害の賠償金は高額になることが多く、10%の差が100万円以上の差につながるということも多いです。
当事務所は被害者の方のために全力で戦っていきます
当事務所では、少しでも過失割合が被害者の方にとって有利になる可能性があるのならば、たとえ物損において、被害者の方にとって不利な過失割合で合意していたとしても、それを覆せるように徹底的に争っていきます。
また、裁判においても、物損において1対9で示談していた案件が、当事務所の弁護士が事故発生時刻(深夜)と同時刻に事故現場に行き、交通量を詳細に調べるなどして、それを証拠として提出した結果、判決では0対10の過失割合が認定されたこともあります。
このように当事務所では、10%という過失割合の差であっても、覆る可能性が少しでもある場合は、現場に赴くことも厭わず、被害者の方のために全力で戦っていきます。ぜひ、当事務所にご相談ください。